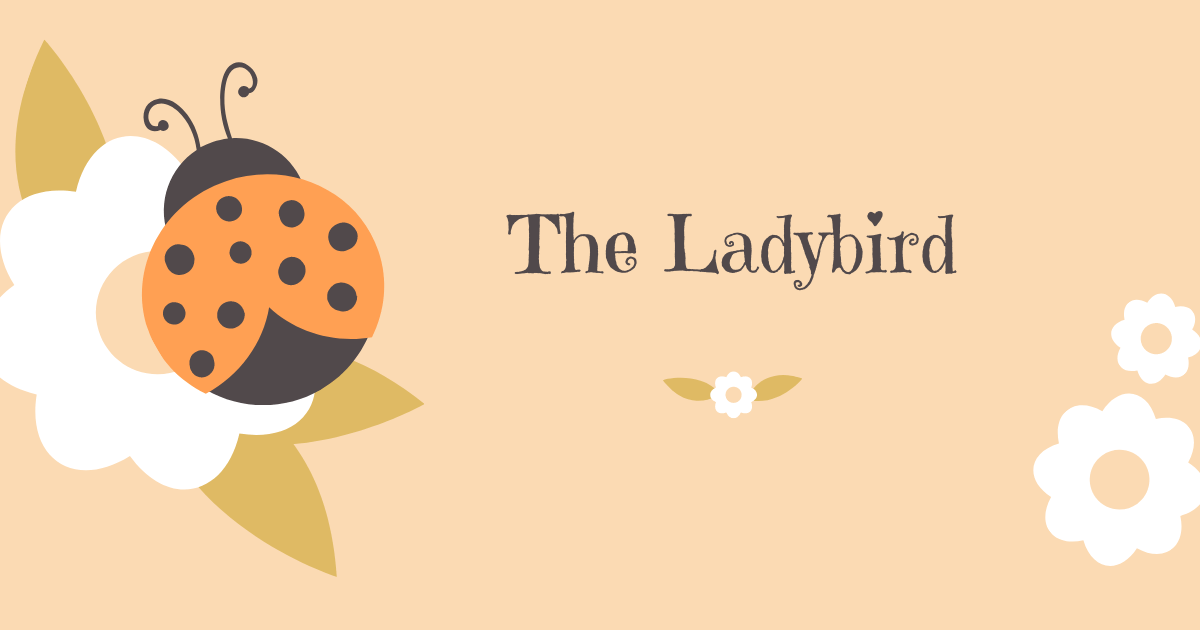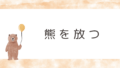『てんとう虫』(The Ladybird)は、イギリスの作家D・H・ローレンスの中編小説(1928年発表)。本記事では『てんとう虫』の登場人物、あらすじ、感想を掲載しています。
登場人物
- ダフニ
激しいエネルギーを心の内に秘めている女性。夫のバジルは東部戦線で行方不明、兄弟たちは戦死、さらに、赤ん坊は死産になっていて、絶望に打ちひしがれている。 - ディオニス伯爵
ボヘミアの伯爵。第一次世界大戦で重傷を負い、ロンドン郊外の病院に収容されている。 - バジル
ダフニの夫。トルコで捕虜になり行方不明になっていた。 - ビヴァリッジ夫人
博愛主義者。長年の間、英国の政治に影響力を持っていたが、戦争末期には政治の中心から離れていた。 - ビヴァリッジ卿
英国の堕落に憤慨している。長年の間、英国の政治に影響力を持っていたが、戦争末期には政治の中心から離れていた。
あらすじ
一九一七年、英国。ビヴァリッジ夫人は敵国の傷病兵を収容しているロンドン郊外ハースト・プレースの病院を慰問する。ビヴァリッジ夫人はボヘミアのヨハン・ディオニス・プサネック伯爵に再会する。ディオニス伯爵は胸の上部を射ち抜かれ、さらに肋骨が砕かれていて、瀕死の重傷を負っていた。
帰路の途中、ビヴァリッジ夫人は娘のダフニのアパートに立ち寄り、ディオニス伯爵と再会したことを伝える。ダフニは、一七歳の誕生日に、金の蛇の彫刻が下部にあり、上部にはてんとう虫をモチーフにした黃緑色の石細工を象嵌した指貫をディオニス伯爵からもらったことを思い出した。
ダフニは病院を訪れ、ディオニス伯爵と再会する。ダフニは病院に通うようになり、ディオニス伯爵は順調に回復していく。ある日、ディオニス伯爵はてんとう虫の指貫でシャツを縫ってほしいとダフニにお願いする。
ダフニの夫バジルが英国に帰還した。バジルの左の頬には傷跡があり、戦争によって、バジルの魂は損なわれていた。
クリスマスの一週間前、ダフニとバジルはディオニス伯爵に会うために、ヴォイニッチ・ホールに向かう。バジルとディオニス伯爵は愛について、権力について、民主主義について哲学的な問答をする。
バジルはディオニス伯爵に興味を抱き、ディオニス伯爵がオーストリアに送還される前に、二週間の滞在の予定でソアズウェイの屋敷に招待した。
ソアズウェイの屋敷では、ダフニとバジルとディオニス伯爵はおたがいに避けあいながら毎日を過ごしていた。ある夜、ディオニス伯爵の寝室から歌声が聞こえてくる。ダフニはディオニス伯爵の歌に、暗黒の世界からの呼びかけに引き寄せられ、ディオニス伯爵の部屋に向かい、ディオニス伯爵の足元にすがりつく。ディオニス伯爵は「暗闇のなかのあなたは私のものです。そして死後のあなたも私のものです(中略)しかし、私はもうすぐ故国へ帰らなければなりません。だから、忘れないでください――あなたは生きているあいだも死んだ後も、てんとう虫の夜の妻なのです」とダフニにささやく。
神話的イメージの交錯
D・H・ローレンスの小説には「夫婦の間に侵入者の男性が登場する」という物語の型があり、『チャタレイ夫人の恋人』が代表的な例である。『てんとう虫』も同じパターンの小説であるけれども、性愛の描写に重点が置かれているわけではなく、むしろ、肉体の存在は影を潜め、神話的色彩を帯びた中編小説になっている。
例えば、『てんとう虫』には様々な神々の名前が直接的に登場する。まず、ダフニの神話的イメージから考えていきたい。
ダフニは、嘆きとか博愛主義のために生まれてきた女ではなかった。すばらしい身体と美しい長い強い脚を持って生まれてきた彼女は、ダフニというよりはアルテミスかアタランタというべき娘だった。
『新集 世界の文学29』ロレンス(伊藤整、伊藤礼訳、1969年)p.361
「ダフニ」はアポロに求愛され、月桂樹に変身した乙女である。「アルテミス」は狩猟を司る女神、「アタランタ」は瞬足の狩人の少女である。いずれもギリシア神話に登場する。この記述は「彼女のなかに激しいエネルギーが蓄積されている」というダフニのイメージに合致する。
さらに、英国に帰還したバジルはダフニのことを「アフロディテ」とか「シベーレ」とか「イシス」に見立てながら賞賛する。「アフロディテ」は愛を司るギリシア神話の女神、「シベーレ(キュベレー)」は小アジアのプリュギア国の生殖の神、「イシス」はエジプトの農事と生殖の神である。元々、アフロディテは生殖と豊穣の女神であると考えられていたから、いずれにせよ、バジルはダフニに対して、豊穣の女神の明るいイメージを抱いている。
次に、ディオニス伯爵の神話的イメージについて考えていきたい。ディオニス伯爵はてんとう虫の紋章についてダフニに訊ねられたとき、「セルベレスの菓子のように」と地獄の番犬「セルベレス(ケルベロス)」に言及している。さらに、人間の世界を打ち倒す「破壊の神」を発見したと語り、ソアズウェイの屋敷の夜の場面において、ダフニにささやいたように、「暗黒の世界」、あるいは「死後の世界」に生きているディオニス伯爵には常に冥王「ハデス」のイメージがつきまとっている。
「彼はディオニソスだった。樹液とミルクと蜜と北方の黄金色の葡萄酒をいっぱいにたたえた酒神ディオニソスだった」
『新集 世界の文学29』ロレンス(伊藤整、伊藤礼訳、1969年)p.389
次に、ダフニは過去のバジルを想起して酒神「ディオニソス」のイメージに重ねている。ディオニソスはギリシア神話に登場する酒神であり、たしかに、昔のバジル―背の高い、頑丈な肉体に恵まれた美青年のバジル―のイメージに合致する。しかし、戦争から帰還したバジルは左の頬に傷を負い、魂が損なわれ、ディオニソスというより、バジル=「バジリスク」(ヨーロッパの伝説上の怪物であり、「蛇の王」を意味する)になってしまっていたのだ。
ところが、ディオニス伯爵の名前が酒神ディオニソスに関連していることは明らかである。しかし、先述したようにディオニス伯爵のイメージは冥王ハデスに近いため、ディオニソスの名称はディオニス伯爵に、そのイメージは過去のバジルに与えられているということになる。
さあ、ややこしいことになってきた。『てんとう虫』の交錯する神話的イメージにどのような説明を与えることができるだろうか。
多分、D・H・ロレンスは特定の神話のイメージを念頭に置いていたわけではなく、神話の中の諸説紛々のごちゃごちゃとしたイメージの流動性自体を借用したのだ(例えば、元々、植物を司る女神のアフロディテが愛の女神に変化していったように)。そのおかげで、『てんとう虫』の登場人物たちは、単一のイメージの枠の中に固定されることを免れ、本物の人間を描写することに成功している。
だから、ダフニは「ダフニというよりはアルテミスかアタランタというべき」であり、ディオニス伯爵は酒神ディオニソスというより冥王ハデスであり、バジルは昔のディオニソスからバジリスクに変化していた。多分、現実世界の人間を固定したイメージの中に捉えることはできないのだ。実際に起こってしまった人類の惨劇、第一次世界大戦がディオニス伯爵とバジルの魂を根底から覆してしまったように、人間存在は単純なものではない。
この小説の最後の場面、バジルが自動車でディオニス伯爵をヴォイニッチ・ホールに送っていくところは印象的である。ダフニという女性を媒介にして、共通の悲劇的な体験を通過したふたつの魂が交流する。ロレンスの小説は「説教者の小説」と呼ばれることがあり、『てんとう虫』も一見したところでは、説教者のディオニス伯爵がダフニを導いているようにみえるけれども、実は、ダフニという女性を媒介にして、戦争に打ちのめされたふたつの魂の交流を描いているのではないだろうか。