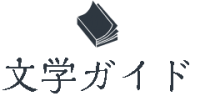アルベール・カミュの代表作『ペスト』は、哲学的な問いと社会洞察をそなえた二十世紀文学の傑作です。フランス領アルジェリアのオランという町で突如として発生したペストの流行と、それに翻弄される人々の姿を描いています。しかし、単なる疫病小説ではなく、不条理や人間の本質を問い直す作品として読み継がれています。
不条理の哲学と『ペスト』
カミュは「不条理の哲学」を提唱した哲学者でもあり、『異邦人』や『シーシュポスの神話』などと同じように、『ペスト』にもこのテーマが色濃く反映されています。作中では、ペストの流行という理不尽な状況の中で、人々がどのように行動し、どのように生きる意味を見出すのかが描かれています。
多様な登場人物と人間の本質
『ペスト』には、さまざまな背景を持つ人物が登場し、それぞれが異なる態度でペストに向き合います。主な登場人物たちを簡単にまとめておきましょう。
- 医師ベルナール・リウー
- ジャン・タルー
- 下級官吏ジョセフ・グラン
- 司祭パヌルー
- 予審判事オトン
- 新聞記者レイモン・ランベール
- 犯罪者コタール
リウーはペストの渦中で医師としての役割を懸命に果たします。保健隊を組織したタルーやグランも微妙な違いはあるものの、基本的には同じ態度です。物語の最初から「不条理」と正面から戦うことを選んでいます。
逆に心情面の変化が興味深い登場人物は、パヌルー、オトン、ランベール、コタールです。
司祭パヌルーはペストを神の懲罰と説きながらも、後に信仰の危機に直面します。秩序の信奉者だった予審判事オトンも不条理に打ちのめされ、変化を迫られます。それから最初は町を脱出しようとしていた新聞記者ランベールは、「個」と「共同体」との間で苦渋の選択を迫られます。ペストの大流行を歓迎していたコタールも最後には…
ポスト・コロナにおける『ペスト』
『ペスト』は、カミュがナチス・ドイツを始めとしたファシズムを象徴的に描いたと解釈されてきましたが、今日では新たな「読み」が生まれています。特に、新型コロナウイルスのパンデミックを経験した現代社会において、『ペスト』の読解は劇的な変化を見せました。疫病による都市封鎖、大衆の恐怖と連帯、情報の混乱といった要素は、まるで現代を予見していたかのように感じられます。また現代社会とは異なっている部分も興味深いために、比較しながら読むことができてしまうからです。
実際にパンデミックを経験してから『ペスト』を読んでみると、私たちは物語の登場人物たちの態度にかつてないほどの「共感」を覚えることになります。今ではもはやペストは象徴ではなく、実体のある具体的な存在になっています。
リウー医師のように冷静に使命を果たすものもいれば、ランベールのように個の幸福と社会的責任の間で葛藤するものもいます。そして、先述したようにパヌルーたちのように信念を問い直さざるをえなかったものたちもいます。そういうわけでマンガのおまけコーナーではありませんが、「あなたはどのキャラクターと似ている?」というキャラクター診断のようなこともできるでしょう。
パンデミックの経験から私たちが学んだことを『ペスト』と比較してみると、現代社会に固有の歴史的な事情が浮かびあがってきます。ポスト・コロナの時代にこそ、『ペスト』を改めて読み直し、その示唆を受け取る価値があるのではないでしょうか。
日本文学の読書案内は「日本文学の名作【50選】源氏物語から村上春樹まで」を参考にしてください。